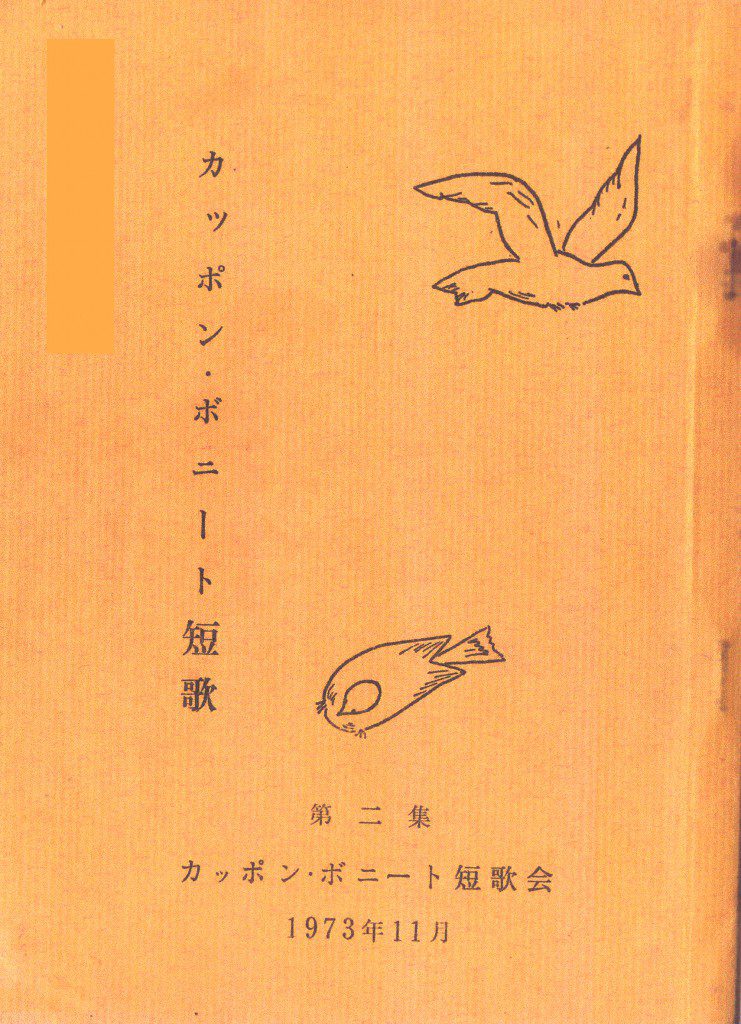バウルー 小坂 正光
二十歳にて人生の目的何ぞやと求道青年宗教書読破す
宗教書全てを読めど青年は悟りに至らず断食をなす
三度目の断食なすうち青年は心の内にひらめきを得る
人生の悟りは愛行奉仕在りと悟るや青年喜びに満つ
若き日の青年多く道求め難行苦行に入り行くなり
「評」小坂氏自身を客観視した作品群である。四首目に良くそれを共感する。「体調悪し」と記されてあるが、折角の御摂養を祈ります。
サンパウロ 坂上美代栄
烏賊船がルーラと気づき霧晴るる頭の体操苦手な私
献立ての決まらぬ日にはモヤモヤと何を作れど半端に終える
道筋の焼そば屋台日系人鍋の中にも火の手が上がる
焼そばを屋台で売れる若き人流るる顎の汗胸で拭く
運んでも運んでも人湧き出づるメトロ構内夕暮れの刻
「評」全く頭の体操に疎い筆者も、一首目に同感。それにしても、政界の今頃には食傷気味で、あゝ又かぐらいで、斜め読みで、赤旗ルーラとは、いやはや、先号の坂上、湯山両氏の作品を読み返している。今回の三首目、「鍋の中にも火の手が上がる」、次の「流るる顎の汗胸で拭く」、ピシャリ言い得ている。
サンパウロ 武地 志津
熊本の地震発生報道の画面は崩壊家屋で埋まる
不意打ちの自然の脅威一瞬に居場所失う住民哀れ
石垣の大きく崩れ熊本城辺りに歩道の段差も目につく
傘をさし夕闇迫る雨のなか給水運ぶ避難の人ら
深刻な予態も動じぬ民族か炊き出しの列に黙とし並ぶ
「評」すでに一週間もつづく、本震、余震。自然災害と人災をはっきりと区別する民族を据えた、五首輝いている。
サンパウロ 相部 聖花
緑濃き大きな葉の蔭まっ白な海芋のつぼみ日ごと伸びゆく
枯れゆくかとも見えたりし蘭の莖に小さきつぼみのふくらむを見る
秋は菊我の持論に違(たが)わずに庭の小菊の咲き初むを見る
メトロ駅一人通れば戸が閉まる新式改札口に戸惑う
通勤時メトロの階段すさまじきどっと流れてゆく人の波
「評」四首目、時代の潮の流れは容赦がない。隠りがちな利などドスンと頭を、そして老眼鏡をおとす所でした。便利に乗せられて出勤する人の流れを、四、五首に据えている。「我の持論」と「庭の小菊」の取合せに、作者が見える。一、二首に、デリケートな眼を感じる。
サンジョゼドスピンニャイス 梶田 きよ
猫の言葉解るようなる娘の様子ながめてあれば心たのしき
八十年もこの地に住みてあっさりとポ語の会話も出来ない私
堪能するほど歌詠みし我短歌にいまだにこもる不思議な力
百歳まで生きたる日本の伯母さんの写真はいつもわが胸にあり
朝市でおぼえし京のお好み焼き今でも家族の大好物よ
「評」ずっと、大和言葉を守ろうとする、「堪能」し続くる心が、一、二首に感じられる。折角、好物のお好み焼きで、体力を付けられる様に。
グァルーリョス 長井エミ子
千年の客足捌き来(こ)し我にまとい付くよな初秋の風
遠路より娘おとなう雨の日にソクセキプリンなるみやげもて
ベル鳴りて午睡の夫(つま)を起こさむとひと呼吸置きノックするドア
別荘はルーラのなりや濃淡のアジサイの咲く側を歩かむ
ブラジルの国情不解(ふか)とたより受く豪雨のごみを片付けし刻
「評」上の句を受ける下句の据えが巧みだ。上下、同時に生れ出るものなのか、詩人の頭には技巧と言うより偶然の閃きなのかも知れない。
カンベ 湯山 洋
遺伝子の組替種子の恩恵はローヤリティや特許料となる
GPSコンピューター装備のトラクター便利とは言え高価過ぎたり
除草剤防虫剤等の効能は支払い時に痛く身に沁む
種肥料農薬農機具収穫まで巨大企業の操るままに
欧米の企業牛耳るこの世界計算されたる豊作貧乏
「評」生き抜いて行くためには巨大企業にも牛耳られ、更には軍需産業が世界をも。
サンパウロ 若杉 好
原始林の中に立ちたる鉄塔が雨後の緑にくっきりと見ゆ
逝く春を汝も惜しむか凋みたるバラの葉かげでシュピンの鳴く
雨嵐吹き去りゆきし野の原に若草青く露をふくめり
食卓の柿は冷たき肌を見せて光るを見れば秋は来りぬ
柿を剥く妻のうなじのおくれ毛のゆらぐを見れば愛しと思う
サンパウロ 上妻 泰子
堪えたえているもの剥がす如くにも背戸のたかむら風にしきなる
淋しさのあふれくる音か宵更けて寺院の鐘が細く鳴りつぐ
娘の便り届きし夜をいつもより杯重ねゆく夫の横顔
声あげて泣きたい想い湧く日なり我のめぐりの落日の色
たどたどと日本文にてつづりたる吾子の便りに目頭うるむ
サンパウロ 上妻 博彦
引潮の残ししあぶく海風に吹かれゆれつつ吹きちぎれ飛ぶ
空になりし古豚小屋に繁茂するカルルもいづれ湯掻きたぶべし
妻子等と一日三度のおんじきをいつもの如く差し向い食む
現身はかくすこやかに在り経つつ糖きびの火酒を夜毎飲みつぐ
雨すぎしこの山道に風たちて大白揚羽かろやかに飛ぶ
カッポンボニート 亀井 勇壮
ロケットが月面におりるこの世代何処にゆくや餅つく兎
霜の朝権兵衛姿で畑にゆき凍てつく新芽そっと撫で見る
日盛りを木かげに憩こう夏の畑モリンガはすでに底をつきたり
雨雲に追いかけられてセボーラを小屋に入るれば夏陽射しくる
真夏陽を受けて無心に遊ぶ子に妻は帽子を持ちてたしなむ
カッポンボニート 亀井 信希
すさみゆく我の心をだれ知るぞそっとたたずみ野の花を見る
夕星を仰ぎつ仕事より帰り歌思う時心みちくる
子沢山時代は過ぎしと言われしも臨月となり初着そろうる
麻酔さめし我を気遣い添う夫にただただ時間問いていたりき
夫の炊きし味噌汁の匂いたちこめて薯の切り目に思わずほほえむ
(注)四十五年も前に、農村の仲間で短歌を初めた、一時は二十名にもなったが、三年ほどで消えてしまった。その二回目の合同歌集のコピーが、ひょっこり手許に届いた。事後承諾として掲載する。
【一つの灯 故・中江 克己】
産業は年事発展して行くが文学は育たないと云われた地方に短歌会が生れて既に幾年、その集積を一本として世に問うという同地方の歌人集団に対して拍手を送ります。それは掌の痛くなる程の、眼頭の熱くなる程の、感激であります。且ての日膝を交えた同じ道に連る方方の顔を、その時に触れ合った心を今限りなく懐しいものとして思い出しています。私個人の実生活の中に、斯うした真実の生活がたとえ一日でもあったという事は、私という人間の存在を如実に実証づけるものであります。
精進と和と探究のあるところに、私共の信条である短歌があの草原の果てまで展けて行く事を祈り、お慶びとします。
一九七三、一、三〇
 ブラジル知るならニッケイ新聞WEB ブラジル発の生情報をほぼ毎日、約20本も配信。サッカー、リオ五輪、デモなど社会情勢、経済、企業、政治、日系社会、日本移民の歴史など各種情報を、豊富な写真付の記事やコラムなどで詳しくお伝えします。
ブラジル知るならニッケイ新聞WEB ブラジル発の生情報をほぼ毎日、約20本も配信。サッカー、リオ五輪、デモなど社会情勢、経済、企業、政治、日系社会、日本移民の歴史など各種情報を、豊富な写真付の記事やコラムなどで詳しくお伝えします。