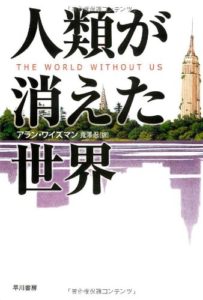新型コロナウイルス拡散の教訓=歴史から辿る「少欲知足」の教え=サンパウロ市ビラ・カロン在住 毛利律子
コロナ騒動で世界再発見

ミヒャエル・ヴォルゲムート(ドイツ語版)『死の舞踏』1493年、版画 「生」に対して圧倒的勝利をかちとった「死」が踊っているすがた。14世紀の「黒死病」の流行は全ヨーロッパに死の恐怖を引き起こした(From Wikimedia Commons)
今年の年明けから始まった新コロナウイルス騒動で、世界中が正体の見えない病原菌の脅威に晒され、厳重な外出禁止令が敷かれて、日々の生活環境も一変した。
こんなことが起ころうとは、予想だにしなかったから、この状況に何時まで耐えられるか。
最先端の文明の利器を使いこなし、豊かで便利で、自由な、戦後の平和状態の暮らしに慣れきっていたところに、突如、疫病の災厄に見舞われている。
数十年に一回の周期で、ヒトには免疫が全くない「新型ウイルス」が出現し、最先端ウイルス学、医療をもってしてもどうにもならず、文明社会は混乱するばかりである。
感染症との闘いにおいて最大の武器ともなるはずのインターネットも、反面、社会の混乱を増幅させるもとになる。人心の乱れによる流言飛語、疑心暗鬼、先行きの不安を煽り、社会に負の連鎖をもたらす。
本当の貧乏は何かと聞かれたら、「食べるものが無い」というのが正しい答えになるであろう。ありがたいことに現状は、食料も安定的に供給され、「衣・食・住」不足で困り果てることも無く、万一そうことになっても一定の支援体制も整っているので、少々の不足不満を辛抱すれば、徒に市民が暴動化することもないであろう。
「人類が消えた世界」
世界がウイルス騒動による閉鎖状況になって以後、写し出された世界の有名な観光地、何処も大混雑でひしめいていた観光客が全く消えた。ニュースでその光景を目の当たりにして不思議な感慨を抱いている。
そして思い出したのが、アメリカ人ジャーナリスト、アラン・ワイズマンが2007年に著した、『人類が消えた世界』である。
その本の主題は、「今の環境破壊がこのまま続くと終にはジオ・カタストロフィ(Geo-catastrophe)「地球の破局」が起こる。正確に言えば、人類が破滅することはあっても、地球が破滅することはない。
むしろ、人類が滅亡すれば、地球は極めて短期間のうちに、再び本来の青い天球の姿を回復するであろう。ジオ・カタストロフィとは、人類が自らの存在基盤を破壊しつくす事であり、そのことが同時に、地球自体にとっては、再生への出発点となるのではないか。
著者は、「自分の周りの環境をすべてそのままにして、人間だけを取り去る。すると、どのくらいの期間で自然は失地回復するのであろうか」と問いつつも、「そもそも、人類が進化しなかったら、地球はどうなっていたのだろうか」ということも知りたい。
このテーマの答えを見いだすべく、世界を駆け巡り、過去に遡り、徹底的な調査を実行した。
その結果、最終章では「地球は、私たち人類のいない世界を寂しがるだろうか」という、地球と人類に対する極めて愛情深いメッセージを残し、人類の英知に改めて呼びかけるのである。
著書には歴史学、生物学、文化人類学といった学際的な調査をもとに、数々のエピソードが網羅され、非常に興味深い。
さて、今、イタリアのベニスの水路が透明になり、魚が泳いでいると住民が嬉しそうに語る姿が写し出される。人間が溢れ、ゴミだらけだった有名な観光地も、昔のヨーロッパ映画で観た閑静な佇まいである。ノスタルジックな風景となった。日本の有名な観光地も、名所旧跡も、全体を見ることができて、改めてその良さを再発見させられるのである。
自分の住む小さな町も、一日中辺りは閑散として静寂そのものである。人の動きが激減したのでポイ捨てゴミ、タバコの吸い殻の量が激減し、通りがウソのように清潔になった。空気もきれいになったような気がする。
「外出自粛」戒厳令を守らなければならないこと自体、自分の人生で全く予想もしなかった出来事であるが、これまでの生き方や価値観を見直さざるを得ないことを痛感し始めているところだ。
今後起こるであろう、将来的様々な不安はあるとしても、今優先すべきは、人混みから離れること。これまでの人間社会の関係を中断、一旦停止すること。
自分の身の丈に合った日常生活を、気持ちを落ち着け、じっくりと見直す。そして、終息後の生活の立て直しを計画する絶好の機会と捉えることにした。
疫病が拡散する諸条件
さて、現時点で起きている問題を考えるとき、疫病が拡散する諸条件とは何かを知る必要がある。そのためには、疫病の歴史を振り返ってみることが参考になる。
まず、感染症増加の根本的原因はどう論じられているのだろうか。
それは、「近代の大規模移動や無秩序に進めてきた大規模開発による環境破壊、国際経済のグローバル化、航空機旅行の移動の高速化などが、世界中に、感染症が容易に蔓延する原因」であり、さらに人類自らが感染拡大の要因になることを次のように要約する。
地球上に生息する生物は、それぞれの種類が一定の数を維持することで生態系の均衡を保ってきた。この、一定の数を維持するという現象が、増えすぎた生き物が、より強い生物に捕食されることで成立するが、人間に関しては、生態系の頂点に達したことにより、他の生物から捕食されることは無くなった。
唯一、人類同士の捕食は戦争である。戦争以外には飢饉があるが、産業革命以降、農作物の供給安定、国際間の交流で、飢饉の被害は減少した。
しかし、病原体だけは人類の誕生から今日まで一定に保つ機能によって、新興感染症となって、人間を襲うというという図式である。
日本の変換期、鎌倉時代に顕著な災厄
現代は、昔と比べると比較できないほど人類の移動は大規模であるが、日本の歴史に限ってみても、古代から、すでに舶来の疫病の記録が残されている。
そのことを知る手掛かりは、世界と同じく宗教史にも現れている。宗教や医学は、災厄との闘いのために生まれてきたと言っても過言でない。
日本の歴史的変換期といえば鎌倉時代である。
公家世界から武家世界への史上初の社会構造の変形であり、武家社会内を覆う根強い疑心暗鬼、権力抗争による小競合いのなかで、新しい国家の在り方を模索した時代であった。
2度に亘る蒙古襲来による国内の攪乱。そして同時に連続して起きた天変地異による天災と疫病の蔓延。飢饉、悪疫、戦乱の、想像を絶する貧困の時代であったと言われている。
それではここで、鎌倉時代の主な天変地夭を年代順に追ってみると、
▼康元元年(1256)8月6日、鎌倉で大風・洪水がおこり、疫病が流行。
▼正嘉元年(1257)5月18日、鎌倉に大地震。
8月1日 鎌倉に大地震、
8月23日 鎌倉に未曽有の大地震、寺社の諸堂が倒壊。
11月8日 鎌倉に大地震。
▼正嘉2年(1258)8月1日 大風雨、諸国田畑損亡。
正元元年(1259)春 大飢饉あり、疫病流行。
▼文応元年(1260)諸国に疫病蔓延。
すなわち、1256年から1260年の僅か4年の間に、大災害が連発し、それに伴って疫病が流行している。
そのときの事態は、「大風や大雨にみまわれ、また地震や洪水、旱魃により作物が実らず、それによって人々は飢えている。そこに伝染病が広がり、悲惨な状況に陥っている。牛や馬はそこら中で死に、その骸骨が路上に散乱。死期を迎えた人々が全人口の半数以上になり、この有様を嘆かないものは誰一人としていない。
巷には飢えて物を乞う者が溢れ、遺体が物見台のように高く積み上げられ、川は遺体を並べると橋となるほどである。
(日蓮聖人『立正安国論』冒頭より)
その惨状は、まさしく言語道断(仏教用語「言葉に表す道が断たれる」)であった。
当然食べ物は無い。医療で救われる手段は皆無。当時の人々にとって、言語道断の救いの無い絶望と、地獄の苦しみから逃れたいとの必死の願いに応じて、人々に生きる希望を語らねばならないという必然から、親鸞、日蓮、道元、法然、栄西等が開祖となる鎌倉仏教が生まれている。
その後も、1596年の伏見地震で豊臣政権が崩壊。1707年の富士山噴火による宝永地震によるほぼ全国に及んだ津波被害、江戸庶民を苦しめた降灰被害など、日本はほぼ毎年、波状的に災害に見舞われている。
このような天災に伴って疫病の拡散し、人々はただ苦しみ、死に絶えていくばかりであった。
遣唐使と共にもたらされた天然痘

735年から737年にかけて奈良時代の日本で発生した天然痘の流行は、「天平の疫病大流行」(てんぴょうのえきびょうだいりゅうこう)と呼ばれる。東大寺大仏殿、盧舎那仏像(奈良の大仏)は、この天平の疫病大流行の後に聖武天皇の命によって建立された(Jakub Hałun/CC BY-SA)
日本は、6世紀以降の飛鳥時代や奈良時代に、遣唐使などの制度で中国との交流が活発になり、そこから具体的に疫病の記録が登場することになった。
痘瘡(天然痘)は古代史の中にも記録があるらしいが、735年、大宰府(現在の福岡)の藤原家が相次いて罹患し死亡したことが信頼されている。その時、政局が大混乱したため、743年、聖武天皇は東大寺大仏造営を開始した。平安遷都直後の808年に大流行した疫病は日本最初のペストと言われるが、詳細は不明である。
鎌倉幕府の三代将軍、源実朝はこの病に罹り、顔貌が醜く崩れ、人前に出ることを疎み、歌の世界に埋没する。しかし、政争から免れることはできず、最期は甥によって暗殺され短い一生を終えた。
天然痘の恐ろしさの原因は、高い死亡率もあるが、その痘の出現による皮膚の病状のすさまじさに人々は怯える。現在では実際、画面などで見ることもできるが、あまりの痛ましさに絶句する。
天然痘は 1万年前には既にヒトの病気であり、インド起源であると思われている。天然痘ウイルスは動物には感染せず、人間にのみ感染する。つまり征服・貿易・戦争・文化交流など、人間の移動ともにもたらされた。エジプトのラムセス5世のミイラの顔に天然痘の痘疱(とうほう)があることから、彼は天然痘で亡くなった名前の分かる最古の患者であると言われている。
天然痘は旧大陸で発生したので、新大陸の人々の間には存在しなかったが、15世紀の大航海時代に天然痘も新大陸の人々にもたらされた。免疫のない新大陸のインディオをほぼ絶滅に追い込んだ病である。
室町から戦国時代にかけては、倭寇という形で日本人の海外渡航が活発になるが、この頃より世界的な疫病に日本も巻き込まれていく。
1495年にイタリア・ナポリで始まった梅毒の流行が、1512年、京都で爆発する。これは、当時東アジア全域に展開していた倭寇に縁るもので、日本国内で大流行し、来航していたヨーロッパ人に甚大な被害を及ぼしたという記録が残る。
脚気、梅毒、麻疹、コレラ、結核などの感染症により、一般庶民が今日のような救済処置を施されることはなく人々は野倒れしていくのである。人々にとって、まさに脅威であった。
今、教訓としての「少欲知足」の教え
冒頭で述べたように、今のような予測不能な事態に直面すると、私たちは自らの生き方や社会のあり様を根本的に見直すことを余儀なくされる。
これまでの現代社会の根本にある価値観、すなわち、「際限のない成長や進歩」を目指すことは人間を無限の可能性へと突き動かす欲望によるものであり、その欲望は文明進歩の原動力となるが、いずれ止まることを知らなくなる。
現代社会を、鎌倉時代の災厄の状況にいた人々と比較すると、私たちが如何に恵まれた時代に生きているかを痛感させられる。
食べ物は不足なく、不調になれば、便利な交通手段で、身近に手当てを受けられる医療施設もある。
住まい、衣服、電気、水にも困らず、通信手段も快適である。これらは、人類が培った文明の証ともいえるが、その恩恵にあずかりながら、疫病終息までを過ごす。何か足りないものがあっても、不自由とは言えないであろう。
仏教に、「少欲知足」という教えがある。その意味するところは、「欲を少なくして足ることを知り、今与えられているものに満足する」ことである。「少欲」とはいまだ得られていないものを欲しないことであり、「知足(足るを知る)」とはすでに得られたものに満足して、心が穏やかであることをいう。
唐の時代の代表的な仏教僧である玄奘は「知足」をさらに深め、「喜足(足るを喜ぶ)」と訳した。
現代人に不足しているものは、思いやりの心であり、過剰なのは得られて当たり前という傲慢である。
職業上とはいえ、医療従事者は不眠不休で働いている。医療保険に入っているからいつでも診るのは当然だ、
強引になるのではなく、ちょっと遠慮してみようではないか。「遠慮」とは「遠くから慮る=きっと大変だろうね」という心遣いである。基本的に、自分の健康は自分で守るものである。
何もすることが無いと、不満足に思ったら、その不満を書き出してみるのも良いかもしれない。概ね、満たされていることを知って満足するであろう。
今の困難を、自分の成長や進歩を考え直おす千載一遇の機会と捉えてみるのも、終息までの過ごし方の一つになるのではないだろうか。