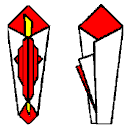特別寄稿=イザベラ・バードの見た「古き麗しき日本」=秋田、山形、津軽、北海道へ=(最終回)=聖市ヴィラカロン在住 毛利律子
三回にわたって取り上げた内容は、明治初期の日本をバードが見たまま描き、昭和の民俗学者・宮本常一が解説したものである。その時代背景から、今日では不適切と言われている表現や言葉が使われているが、当時を知る上で、原文のままとした。
また、バードはすさまじいほどの観察力で社会全般を描いていて、どの場面も大変興味深いことであるが、ここではその中のごく一部を抜粋している。
檜山秋田のこと
イザベラ・バードが現在の秋田県を訪れたころは、「秋田ではなく久保田」といった。秋田となったのは明治20年頃だという。
「秋田」の名前の由来は、飛鳥時代の斉明天皇4年(658年)に阿倍比羅夫の日本海遠征において、この地を訪れ地名を「齶田(あぎた)」と報告したことから始まり、「秋田」の表記で定着した。
宮本常一によると、秋田氏は津軽の十三の出生であった。
一方、若狭(福井県)には武田一族がいた。この一族は700年前に三つの地域で大名になる。若狭武田と、甲斐の国・武田信玄の祖先・甲斐武田、更に、広島県の安芸武田である。
この中の若狭武田が十三秋田氏と婚姻関係を結び、その流れをくむ秋田は檜山へ下って檜山秋田となり、それがさらに分かれて、土崎港の湊秋田が出た。秋田氏の最初の根拠地・檜山で、バードはその武家屋敷に泊まったのであった。
バードは「その家は美しい庭園があり、荘厳な門構えで、洗練されて静かな暮らしをしている家だった」と述べている。
祝いの品には「熨斗鮑(のしあわび)」を付ける
バードは旅の途中で結婚式やお葬式を見ることが多く、様々なしきたりを記述している。ある時、バードの使う移動式ベッドを見たいという人が、お礼にお菓子の贈り物を届けた。その箱の上には「熨斗鮑を紙に包んで水引が掛けられている」。精進ではなく、〝なまぐさ〟であるため、祝いの品ということになる。
人が亡くなったときには「熨斗」を付けない。当時は天皇への献上品にも「熨斗鮑」が添えられていた。現代では、生の熨斗鮑は使われることはなく、「のし」と手書きか印刷がされるしきたりが残っている。漁港から生まれたしきたりということになる。
土崎港の「神明(天照大神)誕生祭」
日本海側には京都などからくる北前船などの漁港があったことから、秋田の土崎港の祭りは山車の上に高く鉾がそびえ、遠くからでも見えるのが印象的だった。それは京都風で、京都に劣らず素晴らしく荘厳で賑やかだった。
祭りの屋台で売っているおもちゃの多さにバードは痛く感動する。日本ほど子供のための郷土玩具の多い国は他にない。しかも貧しげに見える親も気前よく買い与えているのである。
3万2000人の観客に25人の警察官
祭りには、周辺の村々からも人が集まり、総出で3万2000人もいたが、それを警護するのに、わずか25人の警察官で済んだ。観客は一人も酒に酔う者も無く、乱暴者や失礼な態度をとる者もいない。
「どんなに混雑していても、私(イザベラ)が群衆から乱暴されたりすることはなかった」
現代社会では考えられにほど、村人たちが整然として祭りに参加しているのも、バードにとっては驚きであった。
秋田で食べた絶品西洋料理
秋田は古来から瀬戸内からの船がそのまま寄港し、とても洗練されていた。バードは立派な宿で、ビフテキ、カレー、外国からの塩と辛子のついたきゅうりの漬物を食べ、「目が生き生きと輝くような気持ちになった」。
秋田の城下町は繁栄と豊かな生活が漂い、住宅は樹木や庭園に囲まれ、「郊外住宅」は美しかった。つまり、没落の無かった城下町と農村の差は歴然としていた。
外国人技師の活躍
秋田の八郎潟の灌漑工事にはオランダ人技師が活躍した。明治初期には、イギリス、フランス、オランダ、ドイツ人といった多くの外国人が明治政府の招待で各地の治水工事や灯台建設、交通網の整備や教育・文化事業に関わっていた。バードは河川工事で漢字の入った鈍い赤色の着物を着た囚人が黙々と従事するのを見た。
日本の盲人は裕福で尊敬されている
バードは東北の町や村で、晩になると毎日のように盲目の人が特殊な笛を吹くのを見かけた。八郎潟の東の道を青森に向かって進み、秋田の北端で宿泊した時も、何度も按摩の笛の音を聞いた。
バードは日本に滞在中、一度も盲目の乞食を見かけなかった。それどころか、盲人は立派に自立し、裕福で尊敬される階級であった。その職業は按摩、金貸し、三味線を弾く芸事に通じた人たちで、独自の社会構造の中にいた。
そのような職業で得たお金を「座頭金」と言い、庶民の中にはそのお金を借りて成功したり、商売をした人が少なくなかった。
しかし、これはあくまで職業を得て自立している盲人の事であり、そうでなければ、一つとしてよい待遇はない厳しい時代だったのである。また、盲目が増え始めるのは江戸時代半ばからであり、それは性病の一種の淋病の菌が目に入ることに因るといわれて、東北地方に目立って多かった。
ハタハタや鰊の漁港として有名な東北や北海道の漁港には宿泊所、娯楽、遊郭がひしめき、性病の温床となったのである。芸事としては女性の演芸であった三味線となり、男性の盲人や座頭がバチを叩いて弾く特徴的な津軽三味線が人気を博していったのである。
山形の大名町
バードによると、山形は県都。人口2万1千人の繁盛している町で、かなり洋風が進んでいる。政府の建物は混合様式でベランダを付け見栄えがする。県庁、裁判所、進歩した付属学校を持つ師範学校、警察署はいずれもりっぱな道路と町の繁栄にふさわしく調和している。大きな二階建ての病院は150人の患者を収容する予定で、やがて医学校になるが、ほぼ完成していた。
裁判所では20人ほどの職員がほとんど何もしないで遊んでいるのを見た。それと同数の警官は洋服を着て、西洋式の行儀作法を真似ているが、全体として受ける印象は俗悪趣味である。
新庄は大名町で人口5千人を超えるが、みすぼらしい。バードが見てきたこの頃の大名町はどこも廃れていた。
このあたりから、またまたバードは、蚤、蚊、スズメバチ、虻、大蟻にかなり手を焼くことになる。東北でも、垢と洟と皮膚病に苦しむ人々を見た。
先回、当時の衛生状態や医療の劣悪な環境について、「日本人は昔から風呂好きで清潔だと思っていた」という感想が寄せられた。
アカツキビョウ?
これは余談になるが、つい先日読んだ話によると、近畿大学医学部皮膚科学教室主任教授大塚篤司現役医師の報告であるが、「おでこに腫瘍のある高齢男性が来院した。珍しい症状なので若い医師のカンファレンス(会合)に提起した。
すると、それを見た上司が「アカツキビョウじゃないか。おじいちゃんにお風呂に入っているかどうか聞いてごらん」ということだ。それは風呂嫌いの人の肌に着いた垢が腫瘍になったもので、お風呂で石鹸で洗いきれいサッパリ流して治った、ということ。これがアカツキビョウの実態であった。
「現代の快適な住まいに暮らして、コロナ禍で外出も無く、汗もかかない。だから風呂に入らなくてもよいと思いきや、脂漏性皮膚炎、ニキビ、たむし、水虫になりますよ」という医師のアドヴァイスである。
貧しくてお風呂に入れず重い皮膚病になって苦しむ。恵まれた生活でも不潔にしておくと、間違いなく皮膚病になる。特に高齢者は気を付けなければならない、という話である。(AERAdot.メルマガ11・06・2021)
津軽のリンゴと乳牛
弘前はかなり重要な城下町で、旧大名が財政援助した「東奥義塾」の学校長は二人のアメリカ人宣教師が引き継いだ。
二人の功績は、津軽にリンゴを初めて栽培したことと、乳牛飼育を教えたことであった。この乳牛を飼うことを実践したのが笹森儀助という探検家で、津軽藩に仕えた武士だった。
彼は岩木山の麓を開拓して、乳牛を飼い始め、東京で売った。津軽の住民は牛乳を飲まなかったからである。当時、ほとんどの士族授産事業は失敗したが、リンゴと乳牛の飼育は成功した。東北の人々は貧しくても、節度と理性があり、西欧の文化を吸収する力を持っていたと、宮本は解説している。
混浴と秩序
バードは銭湯を覗きに行くと、そこは男女混浴だった。男女混浴であるため、かえって秩序が守られていた。それはイギリスのパブでも同じことが言える。そこでも、型苦しい礼儀作法があり、三助は深く頭を下げて手桶や手ぬぐいを渡した。
この後バードは北海道でアイヌ村に入るが、アイヌの婦人は銭湯で着物を着てお風呂に入っていた。彼女は「裸でお風呂に入ると、神様に失礼になる」というようなことを言った。しかし、江戸時代、男は褌、女性は腰巻をして湯船に入った。アイヌの習俗には、まだそれが残っていたということだった。
北海道アイヌ村に向かう
バードは日本の最北端青森の波止場の洋食屋で「魚肉を一口急いで食べ」て、三菱汽船の船に乗る。それは約70トンの古い外輪船だった。
この時期にもう、青森と函館を結ぶ連絡船が汽船に変わっていたということは興味深いと、宮本は解説している。北海道の開拓村は七飯の洋風の整然とした所と雑然とした所があり、幌別、白老では日本人とアイヌ人の混在した場所がいくつもあり、混血も多かった。平取の日本人村は仙台の士族が開拓したものだった。
ここで、もう一度秘書の伊藤青年についてのバードの印象を引用する。
「伊藤は猛烈に勉強する(当時の若者は必死になって外国文化を吸収しようとしていた)が、彼は極めて日本人的であり、外国のモノは何でも日本の物より劣っていると思っている。
彼は「通訳官」にふさわしい着物を着て、〝見てくれ〟を気にする典型的な日本人である。彼の態度は実に不愉快な時が多い。それでも彼より役に立つ召使兼通訳を雇えたかどうか疑わしい。彼は酒には手を触れず、同じことを二度言う必要もない。いつも私の声の聞こえるところにいる。彼は給料の大部分を母に送っている」
バードと伊藤のアイヌ差別意識
バードの日本奥地旅の核心はアイヌ村(コタン)探訪であり、当時のヨーロッパ人の強い関心でもあった。伊藤は、バードの白人優越意識を基にしたアイヌ観が気に食わない。彼の解釈はそこにあったので、バードのアイヌに接する態度に激しく反抗する。彼は、「アイヌは人間と犬の合いの子だ」と憤慨するのである。
バードは、コタンで文字の聞き取りをした時の状況を次のように語る。
「東洋の未開人と西洋の文明人がこの小屋の中で相対している。しかも未開人(アイヌ)が教え、文明人が習っている。この二つの者を繋ぐ役目は黄色い肌の伊藤で、彼は、西洋文明などはまだ日数も経たぬ赤ん坊に過ぎない、と確信している。東洋文明の代表者として列席しているのである」
この時のことを赤塚憲雄(学習院大学教授)は次のように指摘している。
「バードにとっては、アイヌ民族はキリスト教による救済が必要とされる『子供』と考えている」。つまり「ヨーロッパ的な差別」は、その洗練された身振りゆえに、伊藤のような、むき出しの野蛮な「アジア的差別」に対してある種、美学的な優位に立っている。どちらが差別的か。それを断定するのは非常に難しい。「互いの歴史が複層的であるからだ」と解説する。
今日でも続く極端な自国優越主義、外国人差別意識について考えさせられるところである。
一人の外人の目は、我々に多くのことを気づかせてくれる
以上、バードの旅を辿って点描した。また宮本常一の時代考証は興味が尽きることはない。宮本は多くの場面でバードを賞賛しているが、次の言葉は感慨深い。
「彼女が愛情を以って日本の文化を観てくれた意義は大きいのですが、同時に彼女がこの時期に東京から北海道まで歩いてくれたことは、日本人にとってこの上ない幸せだった。なぜなら、ひとりの外人が見たその目は、日本人が見たより我々に気づかせてくれることが多く、今我々の持っている欠点や習慣はその頃に根を下ろし、知らないうちに我々の生活を支配していることもよくわかるのです。ある意味で我々に一番反省を与えてくれるところではないかと思うのです」
この連載で膨大な記録を纏めるにあたり、非力なために大事なことを見落とし、また言及できなかったことを深く反省している。興味のある方には一度、イザベラ・バードだけでなく明治に日本を訪れた多くの「外国人の眼」を読み返すと、より深く日本文化の再発見に繋がることであろう。(終わり)
【参考文献】
「宮本常一が書いた「イザベラ・バードの旅『日本奥地紀行』を読む」平成14年、講談社オンラインブック(https://www.amazon.co.jp/dp/B00KCL6UX8/ref=dp_kinw_strp_2)