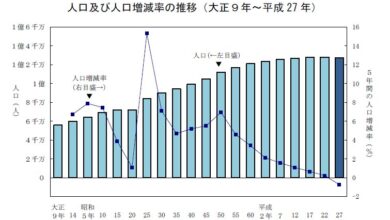《ブラジル邦字紙》 半世紀も選者を務めた星野瞳さんに感謝

「もう年だから辞めようと思った」――ニッケイ新聞の俳壇の選者、星野瞳さん(本名=明、98)は残念そうに語った。「佐藤念腹に推薦されて、50歳ぐらいでパウリスタ俳壇の選者になった」というから、ほぼ半世紀も選者をしてきた。俳句は星野さんの人生そのものだ▼今までに幾つぐらい俳句をつくったのですか、との問いに「数えきれませんね」と笑う。一番のお気に入りの作品として「人戀(こ)へば勿忘草(わすれなぐさ)の芽生える」「しろがねの大角笛を吹く霞」を挙げた。前者は「人を恋しくなったとき、心の中に勿忘草の芽が生える」という心象風景を詠んだもの。後者は「霞がかかっている中を誰かが大角笛を吹いている」というのどかな農村の様子を叙景したもの。星野さんらしい穏やかな息づかいが伝わってくる▼1918年7月に島根県松江市に生まれ、両親と共に1930年2月、11歳の時に渡伯した。ポンペイア時代、25歳ごろからブラジル中を俳句指導して歩いていた佐藤念腹に師事した直弟子だ。念腹師の作で一番好きなのは「珈琲の花明かりより出でし月」。まさに〃移民らしさ〃で右に並ぶものがない風流な作品だ▼「僕はお酒を飲んだことない。楽しみは俳句を作ること。他に趣味はありません。俳句一筋です」。準二世らしく、俳句を通して日本語を学び、日本人としての感性を磨いてきた。選者冥利に尽きることは「俳句を始めて仲間が増えたと、みんなから感謝されていること」という。1986年から俳誌『子雷』を毎月発刊して8年間続け、自分の句集『神有月』も2007年に出版した。今も日本のホトトギス同人を続け、「砂丘句会」「ビラ・マリアナ句会」で指導をする▼日本人にとっての大きな節目である白寿を迎える新年の第1週―そこに掲載される俳壇を最後に選者を引退する。そんな生きざま自体に俳人らしい風流さが漂う。半世紀も俳壇を支え続けてくれた星野さんに心から感謝を捧げたい▼そんな星野さんの指名により、2月から選者を引き継ぐのは小斎棹子さん(さおこ、80、北海道旭川市)だ。「できるかどうか分からないけど、一生懸命がんばります」と謙遜するが、周りの評価は高い▼棹子さんが1歳半の時、父は33歳の若さで結核により亡くなった。「父の吐血でできた血の海の中を、私がハイハイしていたの見て母が卒倒したと聞きました」。凄まじい幼少風景だ。その父が地元で知られたアララギ派の歌人で、「祖父の自慢は『歌人死す』と北海道新聞に掲載された父の訃報でした」と思い出す。初歌集の原稿を枕元に置いたまま亡くなり、友人らが悼んで死後出版した▼札幌で短大1年の19歳、「休学」して叔父夫婦と共に渡伯した。つまり戻る可能性があった。コチア産組の職員になったがポ語ができず、こちらの生活に合わない。「帰国しようかと失意のどん底にいた38歳の時、俳句に出会った」という▼「あの頃は普通の句会でも、とても勉強熱心な人ばかりで、生き字引のようにみんな日本語に詳しかった。すごく熱意を感じ、ブラジルに腰を落ち着けようと決心した」と振りかえる。俳句との出会いが人生を変えた。父の血を引いたのか、いったん作句を始めると「まるで持病のように、寝ても覚めてもそのことを考えている」という▼その情熱をぜひ俳壇に注いでほしいと切に願う。一世、日本語世代は邦字紙と共にあり、邦字紙の華が文芸欄だと思う。消える直前のロウソクの様な、美しくも儚い輝きを俳壇にもたらしてくれるのでは、と期待している。今後の投句先は以下にお願いしたい。(深)
Saoko Kosai
Rua Itatiaia, 75, CEP 04310-010, SAO PAULO,S.P.