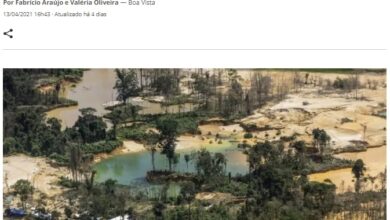臣民――正輝、バンザイ――保久原淳次ジョージ・原作 中田みちよ・古川恵子共訳=(198)
ある日、ミーチが夕食に現れなかった。怒った父は「また、田場の家なのか?」といって、アキミツに迎えに行かせたが、少したって、今日は一日ミーチは姿を見せなかったことを告げた。もう、暗くなりかかっている。ミーチの帰宅がこんなに遅くなったことはない。「いったい、どこに行ったというんだ?」父は一軒ずつ探し回り、マサユキとアキミツも反対のほうの家を探し回った。近所の人たちも心配して手伝ってくれた。月も星もない真っ暗な夜だった。「ミーチ! ミーチ!」と叫びながらマッシャードス区のなかをくまなく探した。なかには危険状態のときにだけ使う懐中電灯をもってくる人もいた。「ミーチ! ミーチ!」といくら呼んでも、答えはなかった。
ミーチは家の奥に置いてある樽のなかにいたのだ。樽はトマトやナスビの収穫期に貯蔵するため使われていた。その日は空だった。彼はこんな小さなスペースに入ったらどうなるか試してみたかった。長いこと歩きつづけて、疲れていた。居心地はすこぶる悪いのだが、そのまま眠りこけてしまったのだ。母の声を聞いて、目が覚めた。いかにも怒っている声だ。彼は恐ろしくなった。なにか悪事を働いて、父親に殴られるなら仕方がない。なにも悪いこともしないのに叱られるのはまっぴらだ。だから、見つからないように息も潜めておとなしくしていたのだ。
母の叫び声は止んだ。「夕飯を食べているのだろと考えた」腹はペコペコにすいていたが、樽に入っていたことで殴られるのがいやで、みんなが寝るまで待とうと思った。あとから台所に忍び込み、かまどの上に残してある食べ物をこっそり食べて、ベッドに入ろうと考えた。「あした、そのことに気づくものはだれもいない」と、身をひそめて、家の明かりが全部きえるまで待つことにした。
ところが、時間が経つに従い、叫び声はいろいろな方向から聞こえ出した。
「ミーチ! ミーチ!」と呼ぶ声に家族以外の声が混ざっている「いったい、なにがおこったというのだ?」と思った。みんなの声のなかに母の声があった。
間違いなく房子の声が近づいてくる。それは怒っている声ではなく、絶望の声だ。自分がとんでもないことをしたことに気付いた。
「はい!」ミーチは日本語で小声で答えた。答えが小さければ小さいほど、母の怒りも和らぐと思った。だれにも聞こえなかったらしく、呼び声がつづく。あいかわらす小声で「はい! はい!」と答えた。樽の横を通ったセーキに小声で返事するミーチの声が聞こえ、「ここにいる! ここにいる!」と叫び、みんなそこに集まった。懐中電灯の光りが樽のなかを照らす。彼はみんなに叩かれるのだろうかと、かがみこんでいた。懐中電灯の方を見て、1、2度瞬きした。光りが強すぎるからだ。泣き顔になりそうになったが、泣かず、黙りこんで、ますます身を小さくした。
彼を樽から引っ張り出したのは母親だ。体が痛かったが「これからもっと痛い目にあわされる」と身がまえた。だが、驚いたことに、みんな大喜びなのだ。すぐにみんなは居間に集まった。正輝は感動して、優しい目をミーチに向けた。こんなに大事にされたのは初めてだ。ネナはずっと泣いていた。ミーチといっしょに過ごせなくなるという恐怖感が去り、感激し、安心して泣いたのか、ただ、嬉しくてないたのか分らない。父親は近所の人たちの協力をねぎらい、飲み物を出し、みんなをドアまで送った。