こんなに新型コロナ禍生活が長く続くとは思いもしなかった。個人の身体機能も生活形態も、すっかり変わってしまった。
運動系機能は確実に低下し、外出しないので反射神経、視覚系、聴覚系の機能低下、生活リズムの乱れによる記憶系の衰えから、脳専門医は高齢者、中高年だけでなく、低学年の児童にまで深刻な「コロナ鬱」を引き起こしていると警鐘を鳴らしている。
新コロナ生活ではオンラインでのやり取りが推奨されているが、それは事務的で、無味乾燥である。
亡くなった肉親を見送るお葬式もできないというのは、人間の尊厳を奪う忌まわしいことではないだろうか。環境の変化は、健康問題だけでなく生活不安・経済不安、過度な感染不安による急性のストレス障害となる。
次の統計は、日本社会の場合であるが、警察庁の自殺統計発表によると、2020年の自殺者は2万919人。2019年まで10年連続で減少していた自殺者数は、一転して増加した。コロナ感染死よりも多い数である。特徴としては、男性より、女性は6976人で前年より885人増。また、年代別では全ての世代で自殺者数が増加したという。
なぜ女性の自殺者が増えるのか。女は子供を産み育て、本能として家庭を守るための愛憎、執着、執念が強く深い。そのための社会的繋がり作りも上手い。それが今のような状況が続くと、
1.深刻な苦痛に満ちた不機嫌さに囚われる。
2.外界に対する興味を放棄する。
3.愛する能力を喪失する。その張りつめた糸が切れる最期のとき、女は自死に突き進むのであろう。
しかし同時に、母は強い。ここでは、極度の「悲嘆体験を超えて安楽を開いた」幾つかのたとえ話を選び、その道を尋ねてみた。
上皇后美智子様のご選歌

今から19年前のことであるが、平成14年(2002年)9月29日、スイスのバーゼルで開かれた国際児童図書評議会創立50周年記念大会で、大会名誉総裁として同評議会から招待を受けた美智子皇后(現・上皇后)が、来賓としてお出ましになられ、ご自身の英語によるスピーチの中で、竹内てるよの詩『頬』を引用された。
それによって、竹内てるよという女流詩人が皇后陛下のスピーチとともに一躍話題になった。周知の事とは思うけれど、『頬』という詩を、まず紹介したい。
生まれて何も知らぬ 吾子の頬に
母よ 絶望の涙をおとすな
その頬は赤く小さく 今はただ一つのはたんきやう(巴旦杏=スモモの一種)にすぎなくとも
いつ人類のための戦ひに燃えて 輝かないといふことがあらう
生まれて何もしらぬ 吾子の頬に
母よ 悲しみの涙をおとすな
ねむりの中に
静かなるまつげのかげをおとして
今はただ 白絹のやうにやわらかくとも
いつ正義のためのたたかひに
決然とゆがまないといふことがあらう
ただ 自らのよわさといくじなさのために
生まれて何も知らぬわが子の頬に
母よ 絶望の涙をおとすな
この詩は次のような背景から生まれた。
「竹内てるよの生涯」

竹内てるよ(本名、竹内照代、明治37年(1904年~平成13年(2001年)は、北海道出身の詩人。
照代の母は芸者であった。父は銀行員で、判事の息子。父の両親は子供(照代)は引き取るが、芸者の母との結婚は許されず、母は海で入水自殺をした。照代は判事の祖父母に引き取られ北海道で育った。その祖父母も父親も結核で亡くす。
照代は、現在の中央公論出版社で事務兼雑用係をして働き始め、20歳で結婚し男児を出産する。ところが照代も結核性脊椎カリエスに罹っていた。赤ちゃんに感染することを恐れた夫の両親は、照代から赤子を引き離そうとした。
まるで自分の境遇と同じことが繰り返されようとしていた。照代は決して子供を離すまいと母子心中を手掛ける。
赤い紐を手に取り、寝ている赤ちゃんの首を絞めようとした。すると、赤ちゃんがパッと目を開け、目の前にぶらぶら揺れる赤い紐を見てにっこりと笑って、紐を取ろうと小さな掌を上げた。
照代は、その無垢でかわいらしい顔を見てハッと我に返った。その薄紅色の頬にポロポロと大粒の涙を落とした。その想いを詩にしたのが『頬』である。
照代の昭和18年2月の手記によると、結核性カリエスを理由に婚家を追われるかたちでの離婚。この詩に登場する最愛の一人息子と生き別れとなる。
照代は、他所の子どもたちの姿を見ては、我が子に思いを馳せて詩を綴る道しかなった。
その後、息子徹也と25年ぶりに劇的な再会を果し、共に暮らすようになるが、徹也は舌癌を患い、若くして病没する。
彼女は、闘病と貧困、療養生活を送るなかで、清廉、清貧、清麗、美しい日本語による多くの詩を残し、2001年(平成13年)2月4日に96歳で永眠した。
上皇后様が、なぜ、国際児童図書評議会創立50周年記念大会で竹内てるよの詩をお選びになったか、その理由は明かされていない。
「でんでんむしの悲しみ」
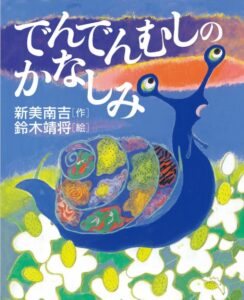
平成五年(1993年)、世間のバッシングなどによるショックから美智子皇后(当時)は声を失った。心因性の失声症だった。声が戻るまで二ヶ月掛かった。葉山でご静養中の時に読まれたのが「でんでんむしの悲しみ」であった。
この童話の内容は――
でんでんむしは自分の殻の中にはたくさんの悲しみが詰まっていることに気づいた。そこで苦しくなって他のでんでんむしに相談した。するとみんなが「わたしのせなかにもかなしみはいっぱいあるのよ」と言った。
悲しみは誰でも持っている事に気づいたでんでんむしは、もう悲しみの殻の重みを嘆くのを止めるのだった、という話。
この童話から、美智子皇后は、「人は誰もが何かしらの悲しみを背負っている」ということを学ばれたということを、平成から令和に変わる3年前の特別番組の中でも仰せになっていた。
どんな人も、その人生には様々な苦しみを繰り返し体験する。
それは、①身体的な痛みを伴う苦、②変化による苦、③何かを成そうとすることに伴う苦の3種類である。
①は、医療的な身体的ケアにつながること。②の苦は、思わぬ事故・事件・病気による身近な人の喪失体験によって、過去の幸福体験が忘れられず、その思い出から生じる苦しみ。③は、善いことをしようとしても自分の思い込みや相手の思いがけない反応によって予想外の展開になってしまうために生まれる苦である。
仏教説話が諭す「すべてを失った女の話」
2500年前に書かれた仏教説話には、真実の智慧が語られる訓話が数多くある。
その中から、「すべてを失った二人の女の悲しみ」を拾ってみた。
◎バーターチャーラーの場合

インドのある町の大富豪には美しい一人娘バーターチャーラーがいた。大勢の由緒正しい家柄の男がこぞって結婚を申し込んだ。その中から最も条件の良い若者との婚姻の約束が交わされたが、娘は幼馴染の下僕に深い愛情を寄せていた。結局彼女は下僕を選び、婚礼の夜に二人は駆け落ちを決行した。
二人は故郷から遠く離れた村に落ち着き、長子が生まれ、続いて次子が生まれそうになると、娘は故郷に帰りたいと思うようになった。夫は帰郷したら厳罰を受けることを覚悟で彼女に連れ添うが、旅の途中で毒蛇に噛まれ死んでしまう。
バーターチャーラーは旅の途中で生まれた赤ちゃんを抱き、旅を続けた。大雨で水かさが上がった川を渡ることになった時、女は、上の子に、自分は先に赤ちゃんを抱いて向こう岸に渡るから、戻るまでここで待つように言い聞かせ、向こう岸に渡ってから、上の子の待つ対岸に向かった。
その時、天空から赤ちゃんを目がけて直下降で下りてきた鷹が赤ん坊を銜えて舞い上がっていくのを見た女は、天に向かって両手を挙げて叫んだ。すると、上の子は自分を呼んでいると思って川に入り、濁流に流されてしまった。
夫と子供二人を一度に亡くし、気が動転した女は故郷を目指して、昼夜歩きとおした。すると、途中で顔見知りの村人に逢った。女はその男に両親の家のことを尋ねると、この大嵐で村は全滅し、大富豪一家も倒れた家の下敷きになって全員死んだ、と言った。
それを聞いて、女は完全に正気を失った。放心して裸で歩く狂女の苦しみや悲しみを、誰も救うことはできなかった。錯乱して放浪していたところで釈尊に出逢って教えを受けた。
彼女は自分の喪失やトラウマによる苦しみから解脱し心の落ち着きを取り戻したいと願って、出家し尼僧となった。
この話は、金持ちの一人娘のバーターチャーラーは、何不自由ない暮らしを捨て、自分に仕えてくれる男と共に新しい生き方を選んだ。その結果の苦難の道から、成長し、生死のことわりを悟る物語である。
◎キサーゴータミーの場合
キサーゴータミーはヨチヨチ歩きをはじめたばかりの子どもを失った。その子の遺体を火葬することを拒み、錯乱した母は遺体を抱いて「この子を蘇らせてくれる薬を知りませんか?」と尋ね歩いた。
ある賢者が彼女を憐れみ「釈尊ならその薬を知っているでしょう」と差し向けた。その薬をほしいと懇願する彼女に対して、釈尊は静かに言った。
「そのためには白カラシの種を一つまみ集めてきてください。ただし、誰ひとり死者を出したことのない家からもらってきたものでないといけません」と巧みな方便をもって答えた。
女は家々を尋ね歩くうちに、白カラシの種はあっても、死者を出したことのない家などないことを理解した。女は釈尊のもとに戻って言った。
「白カラシの種はありませんでした。この世には生きている人々より死んだ人の方が多いのです」と答えた。
釈尊は「あなたは自分の子どもだけが死んでしまったと思っているが、生まれてきたものが死んでゆくのは世の理なのです。死の大王はあきらめの尽きない者たちを苦しみの海へと投げ入れてしまうのです」と語り、それを聞いた女は子供の遺体を手放し、出家して尼僧となった。
ここで注目すべきは、釈尊が混乱した二人の女を、同じ体験を持つ村社会に置くという機会を提供していることである。そして人々はみな、「自分の胸に刺さった矢の痛みを抱えていること」、「この世に来た人の道を知らず、また去った人の道を知らない」ことを二人に教える。
矢の痛みは、悲嘆の道を歩み、失った対象の意味を見出し、それが人生の一部であることを悟ってはじめて癒されるものであることを教えているのである。
しかし、「悟った」という気持ちもまた曖昧である。人間の心は「再発」を繰り返す。生きる過程で怒りや欲求、思い通りにならない無力感、後悔や罪悪感を繰り返し体験しながら生きていく。
★
96歳まで詩を作り続けた竹内照代も、古代の尼僧たちのたとえ話も稀な体験ではない。今現在では、少しも珍しい話ではなくなった。問題は、自分の身の上に起きた時に、冷静に後悔しない行動がとれるかどうかである。
このたとえ話は、人生は悲嘆の繰り返しであること。人間はとても愚かなので、誰もがその体験を通してはじめて、苦を理解する力が熟成される。
それによって、人生に対する希望を抱きながらも、思い通りにならないことに対して絶望することなく歩み続けることが可能になる、と教えている。
【参考文献】
中村元『尼僧の告白』岩波文庫、1982
『静かなる夜明け 竹内てるよ詩文集』月曜社 2003





