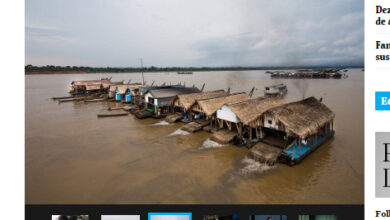《ブラジル》県連故郷巡り=「承前啓後」 ポルト・ヴェーリョとパウマス=(3)=マラリアに五十数回罹る

17日の夕食会に駆け付けてくれた地元の田辺俊介さん(69、鹿児島県)は、ロンドニア日伯文化協会の発起人の一人。6歳で家族と入植し、ずっとポルト・ヴェーリョに住む。29家族のうち、現地残留組は田辺家、須藤家、門脇家、松野家など4、5家族だという。「母親は3人生きているが、父親(家長)の方は全員死んだ」とも。
やはり過酷な生活がたたったのかと思って、マラリアのことを訊ねると、田辺さんは当たり前のように「僕は五十何回罹りましたよ」とアッサリいった。
その一言が全てを言い表している――。
移住地にいた間、年に平均2、3回罹患していたわけだ。先進国ではありえない衛生状態…。「キニーネを飲んでも根治しない。体力が落ちて免疫力が弱ると、すぐに出てくる。体中がブルブルと震えて止まらなくなる」。そんな状況なら、家族の誰かが罹ったら普通はすぐにマナウスやサンパウロなど大都市を目指す。
竹中さんも「熊本では電気も水道もある生活をしていたが、ここではランプ。移住地に沼があって、キレイな湧き水が出て、そこでトマバーニョ(水浴)した。でも、後から皆、マラリアでバタバタ倒れた。皆で助け合わないとやっていけなかった」と振りかえる。
「子供や適齢期の若者が、同じ船で45日間も毎日顔を合わせて一緒に来たでしょ。みな最初は健康。寂しい、哀しい想いを共にして、お先真っ暗な気持ちを慰め合った。だから身近にいる人と結婚し、みな家族になってつながった」と竹中さんは振りかえる。
田辺さんはさらに続ける。「入植3年目から犠牲者が出始めた。日本から持ってきたお金や物資が尽きて、皆やせ細ってきていた。日本から持ってきたモノは売ってお金に換えてしまい、悲惨な状態に。栄養失調になって青白い顔。そこへマラリアの犠牲者が出始めた。特にお年寄りや子供に犠牲者が目立つようになってきた」と振りかえる。
さらに次の一言に衝撃を受けた。「3年目から5年目になると『幽霊植民地』と言われるようになった」。
不思議なことに、そんな話を語る田辺さんの様子はまったく暗くない。「僕らはまだ子供だったから、死人が出ても何が何だかよく分からなかった。むしろ喜んだぐらい。だってお葬式には普段食べられないようなゴチソウがでるでしょ。母に『お葬式はないの?』ってゴチソウ目当てで聞いて、怒られたことがあった。あの頃、飢えていたからね」と笑った。
米国資本フォードはタイヤ用のゴム自給を目指して1920年代からアマゾン河流域に森林を購入し、広大なゴム農場を造成した。自動車産業の隆盛に合わせてゴム需要が世界的に高まっていたからだ。
そんなベルテーラ、フォードランジアには日本移民も戦後すぐに入れられた。その流れの中で、連邦直轄区時代に「日本人にゴム栽培をやらせよう」と企画されたのがグヮポレ連邦移住地だった。
ただし1935年頃から「南米葉枯れ病」がゴムの木に流行しはじめていた。英国は密かにゴムの種を持ち出し、シンガポールやインドネシアに広めたため、ゴム生産は戦後、東南アジアへ移っていった。その流れに逆行するように、29家族はアマゾン河上流に入植した。(つづく、深沢正雪記者)