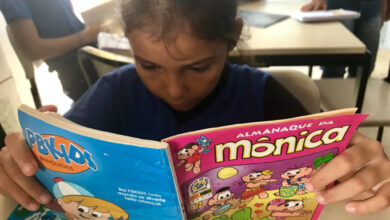臣民――正輝、バンザイ――保久原淳次ジョージ・原作 中田みちよ・古川恵子共訳=(51)
樽、ウシ、正輝が沖縄をあとにしてから、忠道は生きる意欲をすっかり失ったとのことだった。借金の返済もできず、競馬にうつつをぬかしたことで家が破綻し、結婚したばかりの弟、その妻、そして自分の次男を遠いブラジルにやり、家族を離散させた自責の念にさいなまされていた。新城に残った長男の哲夫さえも、賭け金の不支払いで、捕縛される危険にあった。
どうしようもない悪癖が経済的な破綻をもたらしたうえに、自責の念はかられて毎晩、泣き、それまで以上に酒を飲んだ。自分を赦せなかったのだ。正輝は「苦悩のうちに死んでいった」ときかされた。正輝も父を救済する金をもうけることができなかったことで、心を痛めたが、しかし、時だけがとぶように過ぎてしまい、金を貯めて、家族を経済的に救うために帰郷することなどできるはずもなかった。
日本人移民のなかで商業の実務経験があり、短期間で成果を挙げることのできる人間はほんのわずかしかいなかった。移民の大多数は農村出身で、金儲けより、忍耐強いという人たちだったから、一人ひとり、義務をはたしていた。それでも、コーヒー園で何ヵ月か働くうちに、どんなにがんばっても、神戸を出たときの、金を手にするに夢など実現できないと気づいたのだった。
こうして、移民のおおくは正輝の家族のように、悪条件に耐えきれず契約を破棄してにげだした。仕事のわりに賃金が少なすぎるという理由だけではない。農場の仕事はあまりにも過酷過ぎたのだ。日本では自由に働けたのに、ここでは監督官の厳しい監視下におかれていた。
もし、ウシが一週間に何日か家にいることができたら、野菜が食べられるように何か植えただろうが、それはできない相談だった。家に残るのは子どもだけで、正輝はもはや子どもとはみなされなかった。契約で農園にとどまったものたちはみな自分の作物を栽培し、それを売るという願望をもっていた。それで彼らは喉から手がでるほど欲しい現金を手にすることができるのだ。けれども、コーヒー園では生産物は何日か後に金に換算されるのだが、そこから前借金が天引きされるので、いつも不満だけがつのった。
「ブラジルに着いてから、移民は4回から6回、移転した経験をもっている」と経済学の斉藤広志博士は述べ、以下のようにつづけている。
「20年ほどの間に8回以上、転居した場合も少なくない。彼らはよりよい条件を求めて移転した。つまり、移動することでより高い生活水準や可能性を期待したのだ。落ち着くという気持ちはなく、ただ、母国ばかりに目をむけ、『できるだけ早く金をもうけて日本に帰る』という考えを捨てることはなかった」
1915年から1920年にかけて、サンパウロ州のいままでの経済史に存在しなかったことが起こった。大地主が1区画10アルケールの土地を分譲し始めたのである。
「当時としては革新的なこの土地販売法はコーヒー園での契約をおえ、いくらかの金を手にした日本移民に土地購入の機会をもたらした。たいていの場合、これらの土地は植民地を作るため、グループにより買われた」という記述もある。これらの植民地はノロエステ沿線につくられ、1932年には同線のリンス駅の周囲に39の日本人の植民地ができていたという。
保久原家にはこの波にのろうにも、充分な資金をつくる時間がなかった。