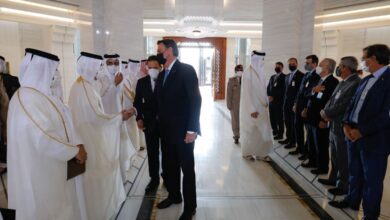新日系コミュニティ構築の“鍵”を歴史の中に探る=傑物・下元健吉(22)=その志、気骨、創造心、度胸、闘志…=外山 脩
1946年4月1日、サンパウロ市内で認識運動の指導者格だった古谷重綱、野村忠三郎が襲撃され、野村が落命した。
その直後、ポ語新聞は一斉に臣道聯盟の特攻隊のテロだと報じた。これは誤報であったが、一般には信じられ、以後、数十年に渡って信じられ続けることになる。
この事件の直後、下元がコチア産組で日本語の週報を発行、外部にも配布、敗戦認識を唱え始めた。筆者は、その週報の保存版にザッと目を通してみたが、説得力のある内容ではなかった。
記事は、ポ語新聞の翻訳や日本の出版物の写し、執筆者の主張が殆どなのである。敗戦認識一本槍であった。襲撃事件の実態調査などは全くしていない。

当時、認識派は「襲撃者は祖国戦勝の狂信者で、認識派の口を封じるためやった」と思い込んでいた(この思い込みも、その後、数十年続く)。
しかし、四月一日事件の襲撃決行者たちの動機は、実は戦争の勝敗問題ではなかった。
動機は、「認識運動開始以来の、邦人社会に於ける皇室の尊厳を犯し、祖国を冒瀆する言動の広まり」「軽率に認識運動を始め、社会的混乱を惹起しながら、それを収拾できないで放置している連中の無責任さ」への怒りだった。
この点につき、半世紀以上も後年、生き残っていた五人の襲撃参加者(実行者四人、企画者一人)が、筆者に、次の様に語っている。
「勝敗問題など、どうでもよかった」
「決起に当たって戦争の勝敗問題を論じたことは一度もない」
認識運動を始めた連中に反省を求め、混乱の収拾を迫ったのだという。
しかし同事件を機に、認識派の指導者格の人々が治安当局に工作して、信念派を大量に検挙、虐待・拷問させた。が、彼らは無実だった。
ために、その工作に対する憤怒が爆発、信念派の認識派に対する襲撃事件が相次いだ。6月以降は、認識派も自警団を組織、警察と組んで反撃に出た。この段階では、もはや相互の憎しみが戦いの動機になっていた。
逆効果だった週報
コチアの週報は、こうした実態の変化に全く気付いていない。
その記事は、襲撃事件については、専らポ語新聞の翻訳に頼っていた。が、ポ語記事は、今日、調べ直すと、いずれの記事も半分以上は間違っている。特に地方新聞は、そうである。事件の殆どは地方で起こっていた。
ブラジル人から見ると、真に判りにくい日本人のことを、短時間に取材して記事にすると、どうしてもそうなったのであろう。が、週報は、その記事を翻訳していた。これでは、内容は真実からドンドン遠のいてしまう。
これでは、信念派の読者に受け入れられる筈はない。こういう場合は彼らの心の琴線に触れる正確な記事を書いてこそ、その心を動かすことができる。週報は、信念派の産青連の盟友を呼び戻すことは出来なかった。逆に遠去けてしまった。
記事を書いていたのは、コチアの職員であったが、下元は目を通していた筈だ。
かくして産青連は、信念派と認識派に分裂した。数は信念派が圧倒的に多かった。ために産青連運動再開の機運は雲散霧消してしまった。
下元は新社会の建設部隊を失った。致命的失敗であった。
彼が終戦1週間後、中央会の幹部職員に指示した「既存の産組を総て解散させ、地方別に組合を組織、その業務を中央会で統括する」という構想も前に進まなかった。
そこまで飛躍した改革は、誰も急にはついていけなかったのである。
それと中央会の他の理事の間には――戦中の下元の功績は認めつつも――彼に対する良くない感情があった。原因はその態度、口の利き方にあった。コチアの組合員や従業員に対するそれと同じで、粗野で荒っぽく無礼であった。
下元自身は、自分は中央会の専務であり、むしろ親しく接するつもりであったろう。が、彼らは、それぞれの組合の幹部であり、誇りもあった。そういうことで、産組再編成構想にも冷淡になってしまった。下元は、ここでも失敗していた。(つづく)